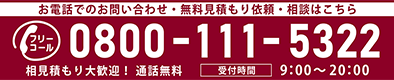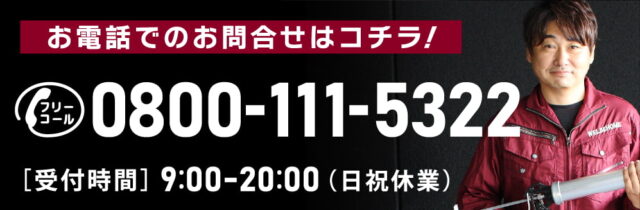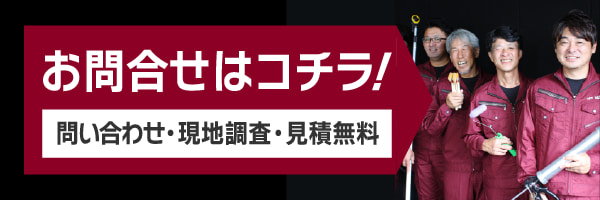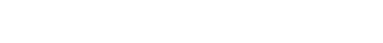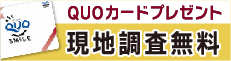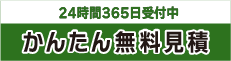塗料別の耐用年数を知って賢く工事!塗装の周期をプロが解説!
2021/10/25

塗装工事をご検討する上で気になるのは『耐用年数』ではないでしょうか?
新築、又は塗装工事後から次に塗り替えが必要になるまで、何年程機能と美観を保持できるかは知っておきたいポイントですね。
また、現在流通している塗料は機能性に優れている物が多く、塗料の種類によっても耐用年数は異なります。
この記事では、塗装工事の耐応年数について塗装のプロが解説致します。
最後までお読みいただけると塗り替えをご検討いただく頻度や、塗料についての理解が深まりますので、是非今後のご参考にご覧ください。
塗装の耐用年数はどのくらい?

塗装の耐応年数はだいたい10~20年が一般的です。
10年の差があるのは、使用する塗料や立地条件によってその劣化具合も異なるためです。
それでは、どの程度の年数を目安にすれば良いか塗料の特徴と合わせて解説してまいります。
ウレタン塗料
ウレタン樹脂が主な成分の塗料です。この塗料は、弾性に優れ、そして艶タイプは光沢も美しいため、どんな塗装工事にも相性が抜群です。この塗料は、1回の工事のコストパフォーマンスにも優れており、工事の予算を抑えたい方におすすめの塗料です。
しかしながら、この塗料は紫外線と水の影響を受けやすく、劣化が早いため、6~8年以内ほどの周期での塗り替えをご検討いただく必要があります。このような結果、工事頻度が増え、長い周期で考えるとかえって高額になってしまう可能性もあることにご注意ください。
シリコン塗料
シリコン系樹脂が主成分の塗料は、現在最も普及している塗料の一つです。この塗料は、汚れに強く、艶も長期間美しく保たれるため、非常に人気があります。耐用年数は約10~15年であることが一般的です。
この塗料が人気である理由は、その優れた耐久性にあります。普通の塗料と違って、このシリコン系樹脂が主成分の塗料は、汚れに強く、長期間美しい光沢を保ちます。この特性は、長い期間にわたって美しさを維持することができるため、住宅や建物の外壁や屋根などに使用されることが多いです。
しかしながら、このような優れた耐久性も、時間が経つにつれて劣化していくことがあります。そのような場合は、ひび割れが発生することもあるため、耐用年数が近づいたら早めに対応することをおすすめします。
ラジカル塗料
全ての塗料には『顔料』が含まれ、この顔料が鮮やかな色を構成しています。また、この顔料は紫外線の影響を受けると『ラジカル』と呼ばれる劣化因子を発生させ、塗料の樹脂成分を破壊していきます。しかし、ラジカル塗料には、この『ラジカル』の発生を抑制する機能があります。ラジカル塗料は、チョーキングやひびの原因となる『ラジカル』の発生を抑制するため、非常に高性能です。
さらに、ラジカル塗料は耐候性が高く、低汚染性があり、防藻や防かび機能にも優れています。近年では、コストパフォーマンスも高いため、注目されている塗料です。また、ラジカル塗料の耐応年数は15年以上と長いのも特徴の一つです。
ただし、使用例が少ない最新の塗料であるため、まだまだ懸念点があると言えます。
フッ素塗料
フッ素系樹脂を使用した塗料で、丈夫で耐久性に優れているため、高層マンションのような外壁等にも用いられています。この塗料には紫外線の影響を受けにくく、低摩擦なので汚れが付着しにくい特徴があり、お手入れも簡単です。
また、フッ素塗料は耐用年数が約15年~20年と長く、長期間にわたって美しい外観を保つことができます。
しかし、初期費用が高額なのが玉にきずで、柔軟性に欠けるため、振動を受けるとひびや割れが生じる可能性もあります。
そのため、この塗料を選ぶ際には、長期的なコストパフォーマンスを考慮する必要があります。また、定期的なメンテナンスを行うことで、耐用年数をさらに延ばすことができます。
無機塗料
一般的に使用されている塗料の多くは有機塗料とよばれ、炭素を含む有機物(石油など)を原料に作られております。
この有機物は紫外線の影響により劣化しチョーキングや色褪せなどの症状を引き起こすのです。しかし、無機物(ガラスや鉱物など)のみで作られた塗料は半永久的に劣化しないため、無機物の耐久性を活かしつつ有機物を配合して作られた塗料が開発されました。この新しいタイプの塗料が無機塗料なのです。
無機塗料は有機物を配合しているため、一般的な有機塗料に比べて高い耐久性を誇ります。そのため、耐用年数が20~25年にもなります。また、無機塗料はフッ素塗料と同様に耐候性が高いため、屋外でも長期間にわたって使用できます。
ただし、無機塗料には若干のデメリットもあります。例えば、無機物の配合が多いため、塗装工事にかかる費用が高額になることがあります。しかし、その耐久性や長期間にわたる美観維持の効果から考えると、無機塗料はコストパフォーマンスに優れた塗料といえます。
塗装工事が必要な周期とは
塗料の機能により耐用年数は大分変わるのです。
しかし、同じような素材の建物でも立地条件によって塗装の頻度が変わることもあります。
たとえば、海沿いにある建物は潮風の影響もあり、山の中腹にある建物は湿気が多い事を危惧しなくてはいけません。
都市部では、車通りの多い通り沿いに建てた建物は常に細かい振動に晒されているので、比較的劣化が早いのです。
塗料と立地にもよりますが、大体10年を過ぎたら一度塗装工事をご検討してみることをおすすめしております。
塗装は建物の衣類です。
破れたりほつれた服を着せていては建物にダメージを与える事にもなります。
塗装の重要性を解説した記事もございますので、ぜひご一読ください。
また、塗装工事が必要か、簡単なセルフチェックの方法もご案内しております。
何か塗装に関してお困り事がありましたらお気軽にリペインターズにお問い合わせください。
この記事を書いている私は『リペインターズ』代表の高橋と申します。
京都市山科区を中心に塗装工事を含むリフォーム業を25年勤めている、塗装と建築の職人です。
営業マンにもわからないような職人の知識をもって、皆様にアドバイスをさせていただいております。