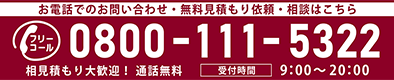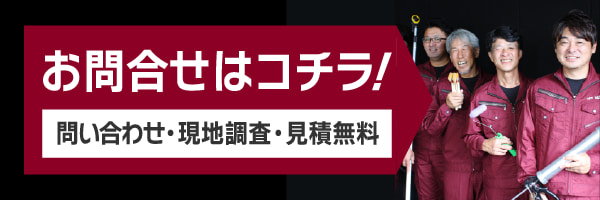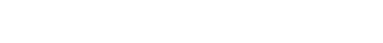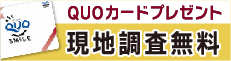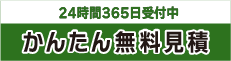京都市街地で多い「集合住宅・長屋」外壁塗装のポイント
2025/11/26

―― 密集地での工事を成功させるために知っておくべきこと
京都市内で外壁塗装をご検討されている方から、よくいただくご相談があります。
それは「うちは隣との距離がほとんどないけれど、塗装はできるのか」というものです。
京都市街地には、昔ながらの長屋や細い道路沿いの集合住宅、戸建てとアパートが密集するエリアが多く、一般的な郊外とは大きく異なる住宅環境が見られます。
当社でも、代表を含む職人たちが日常的にこうした現場に携わっており、施工計画から近隣対応まで、多くの配慮が求められます。
この記事では、京都特有の住宅環境を踏まえた「集合住宅・長屋の外壁塗装のポイント」を、現場目線で分かりやすく解説します。
塗装を検討される際にぜひ参考にしてください。
Contents
■京都市街地に多い「密接・密集構造」が塗装を難しくする理由
京都市の中心部、上京区・中京区・東山区・下京区などには、古い長屋・町家が連なり、1軒ごとの敷地が細長い「うなぎの寝床」構造も多く見られます。
さらに、後から建てられた集合住宅や小型アパートがすぐ隣に接していることも珍しくありません。
● 隣家との距離が数十センチ
外壁まで人が通れないほどの狭い距離で、脚立さえ立てられないケースがあります。
代表いわく「腕だけ壁側に入れて塗るしかない現場」もあるほどです。
● 通路が極端に狭い
資材搬入はもちろん、足場の部材を運ぶだけでも注意が必要です。
● 車両が入らない路地が多い
軽トラックすら入れず、人力で資材を運び入れることもあります。
こうした環境下では、塗装の品質を確保するために、通常よりも緻密な段取りと技術が求められるのです。
■集合住宅・長屋の塗装で最重要となる「足場計画」
塗装の品質は足場で決まると言っても過言ではありません。
ところが、京都の密集地では “組みたい足場が組めない” という壁が立ちはだかります。
◎ 足場を組むスペースが数十センチでも可能か
狭小スペースの場合は、通常のくさび式足場ではなく、特殊サイズの単管、手すり先行型の小型ユニット、重量物を使わない軽量足場などを組み合わせて対応します。
◎ 隣家との接触を避ける“ゼロ距離配慮”
壁同士がほぼ隣接している場合、足場の支柱を立てる位置が限られるため、職人同士が慎重に検討します。
場合によっては隣家様の敷地を一部だけお借りする交渉も必要です。
◎ 長屋では一部だけではなく“全体で考える”
長屋は構造がつながっているため、一軒分の工事であっても、足場を共有する建物に影響が出ることがあります。
端部から順に組み上げ、近隣住民への動線確保を徹底します。
代表の実体験として「長屋の入り口が一つしかない現場では、日中も住民の出入りを止めないよう細かく段取りした」と語っています。
■飛散防止・臭気対策 ― 京都の密集地ならではの“近隣配慮”
京都市の特性として「住宅同士の距離が近い+風の通りが複雑」という点があります。
そのため、飛散(塗料・高圧洗浄の水)や臭気への配慮は欠かせません。
● 高圧洗浄の飛散
狭い裏側でも、飛散防止シートの二重掛け・下水への養生を徹底します。
裏庭がなく隣家とすぐ接している現場では「手洗い洗浄(ブラシ洗い)」を採用することもあります。
● 塗料の臭い
水性塗料が主流とはいえ、密接住宅では近隣の洗濯物に臭いが付く可能性があるため、事前の説明は必須です。
● 風向きの読み
京都は盆地で風向きが変化しやすいため、塗装のタイミングは天気予報以上に現場の“風”を見る必要があります。
代表は「その日の昼前の風向き次第で工程を1日入れ替えたこともある」と話します。
■壁材の種類を正確に見極める ― 京都の集合住宅は多様な外壁
京都の街中には、築年数・構造・外壁材が入り混じった集合住宅が多く存在します。
モルタル外壁、サイディングボード、ALCパネル、タイル外壁、漆喰仕上げの町家、木部主体の古い町家
同じ並びでも、隣は昭和のモルタル、隣は平成のサイディングということも珍しくありません。
● 町家や長屋は「湿気の逃げ道」を残すことが重要
調湿効果が高い建物が多く、過度な防水や密閉は逆効果になることもあります。
通気性塗料・シリコン系・ナノ系塗料など、建物の性質に合わせた塗料選択が必要です。
● ALCやタイル外壁は“ひび割れ”の把握が重要
集合住宅は地震や交通振動で揺れやすく、ひびの入り方に特徴があります。
表面だけではなく裏側まで確認し、適切な下地処理を行います。
■養生と動線確保 ― “住みながら”工事するための工夫
集合住宅や長屋は、住人の生活が続く状態で工事を進めるのが一般的です。
● 廊下・通路の養生
足場の柱が住民の通路を狭めるため、通行可能な幅を確保しながら、滑りにくい養生材を使用します。
● 洗濯物の干し場対策
ベランダが使えなくなる期間は、事前に日数を明確にお伝えします。
● 工事中の騒音・振動
高圧洗浄・下地補修など、音が出る工程は時間帯を調整し、周囲の生活リズムを尊重します。
こうした配慮が行き届くことで、近隣トラブルを防ぎ、スムーズに工事を進めることができます。
■色選び ― 景観条例と“京都らしさ”を踏まえた判断が必要
京都市には、一部地域で「景観色」の制限や推奨色が設けられています。
京都で人気のある配色
・黄土色・ベージュ系の和風色
・深いブラウンやグレー系
・黒系のモダン和風
・木部との相性を重視した抑えめトーン
代表は「派手な色を選ぶお客様でも、最終的には“京都らしい落ち着き”に寄ることが多い」と話します。
京都で使用可能な塗料の色はコチラの記事をご覧ください!
■工期と費用 ― 密集地ならではの追加要因
● 工事日数は郊外よりも長め
資材搬入の難しさ、足場の工夫、養生の手間などから、同じ建物規模でも工期は 1~3日ほど長くなります。
● 追加費用が発生しやすい
道路使用許可
車両が入れない場合の人力搬入
特殊足場
など、京都市街地特有のコストが重なることがあります。
ただし、これらを放置して安値優先の業者に依頼すると、
「足場が十分に組めずに塗りムラが出る」「塗膜の耐久性が落ちる」
など、後々のトラブルにつながることが多いので注意が必要です。
■実際の現場
京都市中京区の閑静な路地に建つ戸建住宅にて、外壁塗装工事を行いました。
現場は細い生活道路に面しており、近隣への飛散や臭気への配慮が欠かせない環境でした。
隣接する建物との間は、狭い所で数センチメートルしかなく、支柱を上手く確保しながら慎重に足場を設置しました。


建物はモルタル壁と増築部分のサイディング壁が混在していたため、それぞれに最適な下塗り材を使い分け、丁寧に下地を整えてから上塗りを実施。
クラック補修や養生も慎重に行い、雨水の侵入を防ぐための処理を徹底しました。


足場設置後は高圧洗浄からスタートし、雨天時でも施工品質に影響が出ない工程は計画通り進行。
仕上げ塗料には耐久性と防水性に優れた材料を採用し、付帯部までしっかり塗装しました。


日当たりの弱い路地裏ながら、風通しに恵まれ乾燥も順調で、暖色系のベージュに塗り替えた外壁は明るく温かみのある仕上がりに。近隣の皆様のご協力もあり、安全かつ円滑に完工いたしました。
■まとめ ― 京都の集合住宅・長屋の塗装は、“経験者の技術”が結果を左右する
京都の街中で外壁塗装を成功させるためには、次の3つが非常に重要です。
密集住宅に慣れた業者であること
足場・養生・飛散防止などの細やかな配慮があること
町家・長屋・集合住宅の壁材や構造を正しく診断できること
当社では、代表を含む職人全員が京都市内の複雑な現場経験を重ねており、
「狭くても塗れる」「古くても守れる」「近隣に迷惑をかけない」
という姿勢を大切にしながら工事を行っています。
京都らしい住宅環境での外壁塗装は、環境・壁材・構造すべてが特殊です。
そのため、単に“塗るだけ”ではなく、建物と暮らしを守るための総合的な判断が必要です。
外壁の劣化が気になる、雨漏りが心配、どこに相談すればいいか分からない——
そんな方は、一度お気軽にご相談ください。
現地調査の段階から、“京都に暮らす方のための塗装”をご提案いたします。